遺産相続でよく起こる6つのトラブル事例|相続トラブルを防ぐ2つの対策も紹介

遺産相続をするときに注意したいのが、相続人の間で起こる相続トラブルです。相続トラブルは、意外と起こりやすい実態があります。そのため、将来的に遺産を相続する・相続してもらう予定がある場合は、トラブルを防ぐための対策や準備をしておくことも大切です。
今回は、相続トラブルが起こる割合を確認したうえで、遺産相続時によくあるトラブル事例を6つ紹介します。遺産相続に向けて準備を進めている方は、ぜひ参考にしてください。
INDEX
相続トラブルが起こる割合

遺産相続時にトラブルが発生したかどうかは、人によって捉え方が異なる部分もあります。ただ、相続に関する調査結果を見ると、意外と多くの相続でトラブルが起きていることがわかります。
たとえば、一般社団法人 相続解決支援機構が実施した調査結果によると、調査対象者の78.7%が「相続トラブル経験あり」と回答しています。また、不動産相続が原因で揉め事になった割合は、全体の40.8%です。
これらの数字を見ても、遺産相続ではトラブルが非常に起こりやすいと考えたほうが良いでしょう。
遺産相続でよくあるトラブル事例

相続トラブルには、さまざまな種類や事例があります。将来の遺産相続に向けて準備をする際には、よくある事例に目を通し自分に関係がありそうなことを想定したり、対策を講じたりしておくことも大切です。
今回は、6つの相続トラブル事例を紹介しましょう。
主な遺産が自宅の土地建物だけだった
被相続人の財産が自宅の「土地建物だけ」の場合、複数の相続人の間で遺産を分けることが難しくなります。しかし一般的には、特定の相続人が自宅を取得する代わりに、ほかの相続人の代償金を支払う代償分割という方法が取られることが多いです。
ただ、たとえば、自宅を取得する長男に代償金を支払えるだけのお金がない場合、ほかの相続人に支払いができず、相続トラブルに発展することがあります。
被相続人に多額の借金があった
相続人には、「被相続人である親が亡くなったら、土地や金銭などの相続ができるはず……」といった期待があることも多いです。ただ、そんな被相続人に多額の借金があった場合、土地や現金などの「プラスの財産」と、借金返済義務などの「マイナスの財産」の両方を引き継がなければならなくなります。
国では、こうした問題が生じたときのために、相続放棄と限定承認という制度を用意しています。相続放棄の場合、借金を含めたマイナスの財産とプラスの財産を両方放棄するイメージです。相続放棄をする場合、裁判所に申し立てを行う必要があります。
相続人調査で知らない異母・異父兄兄弟が見つかった
遺産相続は、すべての相続人の間で行われるものです。
たとえば、父・母・娘・息子の4人家族で父親が亡くなった場合、相続人は母・娘・息子の3人になります。ただ、ここで一つ注意点があります。それは、この父親はかつてほかの女性と結婚をしていて、その女性との間に生まれた子どもを認知していたなどの場合、その子どもにも相続の権利が生じる点です。
相続人調査によって異母兄弟姉妹の存在が明るみになれば、当初のイメージでの相続が難しくなり、トラブルに発展することもあります。
連絡がとれない相続人がいる
先述の異母・異父兄弟姉妹にもいえることですが、相続人同士は、連絡を取り合ったりお互いの居場所を教え合ったりしているとは限りません。
特に、家族仲が悪かったり、駆け落ち同然で家を出ていったりした場合は、「もう数十年連絡をとっていないし、どこで何をしているのかまったくわからない」といった状況になることもあるでしょう。
遺産分割協議は、相続人全員で行うものです。
そのため、連絡が取れない相続人がいた場合、いつまで経っても遺産分割が終わらなくなってしまいます。相続人との連絡が取れない場合の対策もいくつかあるのですが、不在者財産管理人の選任や、遺産分割調停の申し立てをするとなれば、かなり手間や時間がかかることになります。
特定の相続人だけ優遇されていた
法定相続人が複数いる場合、法定相続分にもとづき平等に財産を分けるのが原則です。ただ、以下のようなケースに該当する場合、特定の相続人だけが優遇される状況への不満から、相続トラブルに発展することがあります。
- 被相続人が生前に、同居の娘にだけ贈与や遺贈を行っていた
- 同居の息子が生前介護をしていたことで、寄与分を主張してきた など
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加への貢献をした人の相続分を増やす制度です。寄与分の考え方からいえば、②の主張は正当なものとなります。
実際の相続では、「自分だけたくさんの財産を受け取るのはズルい」や「寄与分などという制度があるなら、自分も介護をやっていた」などの不満や嫉妬が起こりやすいです。
複数の遺言書が出てきた
遺言書の有効性や不公平な内容も、相続トラブルの原因になりえます。
たとえば、認知症である母が複数の遺言書を作成し、その内容に差異があった場合、「どちらの内容で相続するか?」で揉め事が起こることがあります。その遺言書が「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言」の2種類だった場合、後者は公証人が関与するため裁判などでも無効になりにくいです。
ただ、ある相続人にとっては自筆証書遺言書の内容が望ましい場合、有効性とは関係なく「公正証書遺言の内容に自分は納得できない」などのトラブルになることもあります。
遺産相続のトラブル事例とその説明
| トラブル事例 | 説明 |
|---|---|
| 自宅の土地建物だけ | 自宅だけだと遺産分けが難しく、代償金が支払えずトラブルに。 |
| 多額の借金があった | 借金も引き継ぎ、相続放棄や限定承認が必要になる。 |
| 異母・異父兄弟が発覚 | 異母兄弟が現れると、相続が複雑になりトラブルが起きる。 |
| 連絡が取れない相続人 | 連絡がつかないと遺産分割が進まず、調停が必要になる。 |
| 特定の相続人だけ優遇 | 生前の贈与や介護で特定の相続人が優遇され、不満が起きる。 |
| 複数の遺言書 | 遺言書に差異があると、相続内容で揉める可能性がある。 |
相続トラブルを防ぐ方法

遺産相続時のトラブルには、事前の準備で防げるものと、異母兄弟姉妹の発覚といった対策や想定ができないものがあります。ただ、相続トラブルを最小限にするためには、被相続人が元気なうちにできる限りの準備や対策をしておくことが大切です。
ここでは、比較的すぐに実践できる2つの方法を紹介しましょう。
公正証書遺言を作成しておく
まず、被相続人の希望や考えを、遺言書に残しておきましょう。遺言書の記載内容は、遺産相続時にも優先されることになります。また、遺言書の内容で相続するとなれば、相続人による遺産分割協議は必要ありません。
ただし、遺言書の内容に納得できない相続人がいた場合、被相続人の死後にトラブルが生じることがあります。そのため、もし可能であれば、被相続人が元気なうちにすべての相続人にその内容を伝えておくことも一つです。
作成した遺言書は、専門家に管理・保管してもらうことも検討したほうがよいでしょう。
相続の専門家に相談をしておく
たとえば、以下のように相続トラブルが起こる可能性が想定できるのであれば、被相続人が亡くなる前に弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談しておくことも一つです。
- 被相続人が遺言書を書いてくれない
- 相続人のなかに、もう20年連絡がつかない人がいる
- 借金が多い被相続人の財産を相続すべきか悩んでいる
- 自分だけ多くの財産を相続しようとする相続人がいる
たとえば、20年連絡がつかない相続人への対策なども、被相続人が亡くなる前に行動を起こしたほうが、相続開始以降の負担が少なくなります。また、法律の専門家に相談をすることで、一般人では見落としがちなポイントや対策も見つけやすくなるでしょう。
遺産相続でよく起こるトラブルのまとめ

相続では、相続人が一度も会ったことがない「異母兄弟姉妹」や「内縁の妻」などが絡んでくるケースもあることから、法定相続人である親族にとって想定外のトラブルが起こりやすい実態があります。
また、近年では、いわゆる独居のお年寄りも増えていることから、相続人である親族とのコミュニケーション不足などの要因で相続トラブルが起こりやすくなっている側面もあるでしょう。
相続は、大半の人に関係するものです。自分が将来的に「相続する」「相続してもらう」ことを想定し、早めの準備やトラブル対策を講じてみてください。
マネクラではお客様のお金に関する相談に無料で対応しております。マネクラFPがしっかりとヒアリングさせていただき、お客様にあったプランニングをさせていただきます。是非お気軽にお問い合わせください。
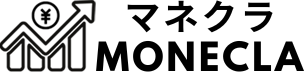
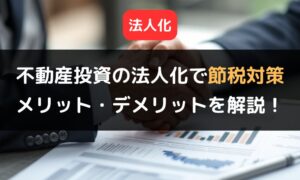 不動産投資の法人化で節税対策!メリット・デメリット、手続き方法を徹底解説
不動産投資の法人化で節税対策!メリット・デメリット、手続き方法を徹底解説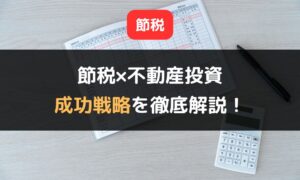 【2025年版】節税×不動産投資の成功戦略!プロが教える減税テクニック
【2025年版】節税×不動産投資の成功戦略!プロが教える減税テクニック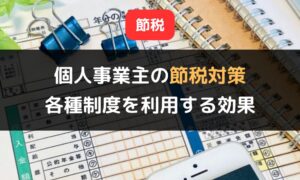 個人事業主におすすめの節税対策5選|各種制度を利用する効果・メリットも詳しく解説
個人事業主におすすめの節税対策5選|各種制度を利用する効果・メリットも詳しく解説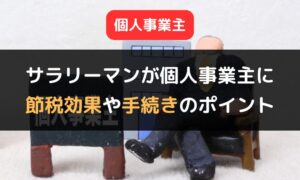 副業サラリーマンが個人事業主になる|期待できる節税効果や手続きのポイントを解説
副業サラリーマンが個人事業主になる|期待できる節税効果や手続きのポイントを解説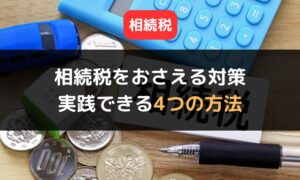 相続税をおさえる4つの対策|土地住宅などの不動産がある場合のおすすめ方法も紹介
相続税をおさえる4つの対策|土地住宅などの不動産がある場合のおすすめ方法も紹介